ご興味がありますか?今すぐご連絡を
ご連絡の際は右のフォームをご記入いただくか、下記メールアドレスまで直接ご連絡ください。
sales@senecaesg.com
温室効果ガス(GHG)プロトコルは、温室効果ガスの排出量を測定・管理するために不可欠な包括的なグローバル・フレームワークである。1998年に世界資源研究所(WRI)と持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)によって発足したこのプロトコルの主な目的は、企業や組織が効果的に排出量を測定・管理するための標準化されたアプローチを提供することである。これにより、企業は気候変動への影響を十分に把握し、最小限に抑えることができる。この議定書は、気候変動に対する意識の高まりと、早急な行動への切迫した要求から、最近になって注目されるようになった。より多くの組織が持続可能性に忠誠を誓い、環境への貢献に関する透明性と説明責任の必要性を強調している。その結果、GHGプロトコルは、気候変動に対する世界的な闘いにおいて不可欠な道具となり、効果的な気候変動対策戦略を促進する一貫性のある比較可能な排出量報告を促進している。
GHGプロトコル排出量2は、排出量の測定と管理のための明確な枠組みを提供するために設計されたグローバル温室効果ガスプロトコルの重要な要素です。プロトコルのこのセクションは、環境への影響を理解し、グローバルスタンダードに準拠することを目指す組織にとって不可欠である。その詳細な方法論と遵守ガイドラインを通じて、GHGプロトコル排出量2は、気候変動を緩和するための世界的な取り組みにおいて重要な役割を果たしている。
このブログでは、組織が間接的な温室効果ガス排出量をどのように正確に測定、報告し、最終的に削減できるかに焦点を当てながら、スコープ2排出量の複雑さを探っていきます。
GHGプロトコル排出量2には、購入電力、蒸気、暖房、冷房の消費による排出が含まれる。多くの企業にとって、電力の調達は温室効果ガス排出量のかなりの部分を占めており、排出削減の絶好の機会となっている。スコープ2を評価に含めることで、企業は、電気料金や温室効果ガス排出費用のシフトに関連するリスクと利益を効果的に測定することができる。
GHGプロトコルの排出量2は、他のGHGプロトコルのスコープと比較すると、明確な課題と機会を提供する。企業が直接管理できるスコープ1の排出量とは異なり、スコープ2の排出量では、企業はサプライヤーやユーティリティプロバイダーと協力しなければならない。この相互作用は、特に再生可能エネル ギー慣行やエネルギー効率イニシアチブの採用な ど、大幅な持続可能性向上の道を開く。これとは対照的に、Scope1排出量は企業が直接排出するものであり、Scope3排出量は、企業のバリューチェーンで発生するその他のすべての間接的な排出を含むが、測定と管理において独自の課題があり、持続可能な変化を促進するScope2の複雑性と可能性をさらに強調している。
GHGプロトコルには、京都議定書で定義され、一般に「京都ガス」と呼ばれる6つの主要温室効果ガス(GHG)の測定と報告が含まれる。これらの温室効果ガスは、地球温暖化と気候変動の重要な原因となっている。ここでは、議定書に含まれる各温室効果ガスについて説明する:
1. 二酸化炭素(CO2):CO2は、主に石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料の燃焼によって、人間の活動によって排出される最も一般的な温室効果ガスである。また、森林伐採やその他の土地利用の変化によっても排出される。
2. メタン(CH4): CH4は、石炭、石油、天然ガスの生産や輸送の際に排出される。また、家畜の消化、農業活動、埋立地、嫌気性条件下での有機廃棄物の腐敗によっても発生する。
3. 亜酸化窒素(N2O): N2Oは、肥料の使用、家畜の糞尿管理、化石燃料の燃焼、アジピン酸の製造や廃水処理などの特定の産業プロセスなど、農業や産業活動から排出される。
4. ハイドロフルオロカーボン(HFC): HFCは、オゾン層破壊物質の代替物質として、主に冷凍、空調、発泡、その他の産業用途で使用されている合成温室効果ガスである。CO2に比べて地球温暖化係数(GWP)が高い。
5. パーフルオロカーボン(PFC): PFCは、アルミニウム製造、半導体製造、電子機器製造など、さまざまな産業用途で使用されている合成ガスである。GWPが非常に高く、大気中での寿命が長い。
6. 六フッ化硫黄(SF6): SF6は、主にサーキットブレーカーやスイッチギアなどの送配電設備に使用される合成ガスである。GWPが非常に高く、大気中に何千年も残留する可能性がある。
これら6つの温室効果ガスを排出インベントリや報告書に計上することで、組織は気候変動への貢献を正確に評価し、環境への影響を軽減するための戦略を策定することができる。
GHGプロトコル排出量2を支える方法論は、エネル ギー消費による炭素排出量の算定を重視している。重要な原則の一つは、「市場ベース」アプローチと 「場所ベース」アプローチを区別することであり、 組織は、契約手段(例えば、再生可能エネルギーの 購入)の効果を報告された排出量に反映させることが できる。
ロケーションベース法(グリッド平均法とも呼ばれる):
市場ベース法(契約商品法とも呼ばれる):
これら2つの方法論は、組織がデータの利用可能性、報告目標、持続可能性の目的に最も合致するアプローチを選択できる柔軟性を提供している。
GHGプロトコルの排出量2に基づく排出量の算出には、エネル ギー使用に関するデータ収集、適切な排出係数の選択、関連する換算係数の 適用など、いくつかのステップが含まれる。このプロセスは綿密であり、炭素インベントリの完全性を確保するために正確性と透明性が要求される。
GHGプロトコル排出量2への準拠には、計算と報告のための標準化された方法論の遵守が必要である。 温室効果ガス排出量.これには、以下の排出量を包括的にカバーしている。 スコープ1, スコープ2そして、潜在的に スコープ3 排出源。組織は、正確なデータの完全性を維持し、排出量データを検証するための品質保証手順を受けなければならない。排出データと方法論の適時報告と透明性のある開示は、説明 責任と利害関係者の理解のために不可欠である。コンプライアンスには、規制要件を満たし、 排出量管理手法の継続的改善を実証することも含まれ る。全体として、GHGプロトコル排出量2基準への準拠は、 排出量報告の透明性、信頼性、説明責任を強化し、 持続可能なビジネス慣行と環境責任を支援する。
GHGプロトコル排出量2は、環境保護活動や企業の持続可能性への取り組みにとって重要な焦点となる。そのフレームワーク、適用範囲、遵守メカニズムを解き明かすことで、気候変動に対して意味のある行動をとるためのロードマップを提供する。企業にとって、GHGプロトコル排出量2を使いこなすことは、単に規制上の必要性というだけでなく、持続可能性を追求する上での戦略的優位性でもある。
野放図な排出がもたらす結果と格闘する世界において、GHGプロトコルは希望の光となる。GHGプロトコルは、二酸化炭素排出量を測定、管理し、最終的に削減するためのツールを提供してくれる。環境活動家にとっても企業リーダーにとっても、GHGプロトコル排出量2の原則を理解し実行することは、経済成長と環境スチュワードシップが両立する、より持続可能な未来への一歩となる。
情報源
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2023-05/GHGP%20scope%202%20training%20%28Part%201%29.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2023-03/Scope%202%20Guidance.pdf
ポートフォリオのESGパフォーマンスを監視し、独自のESGフレームワークを作成、より良い意思決定をサポートします。
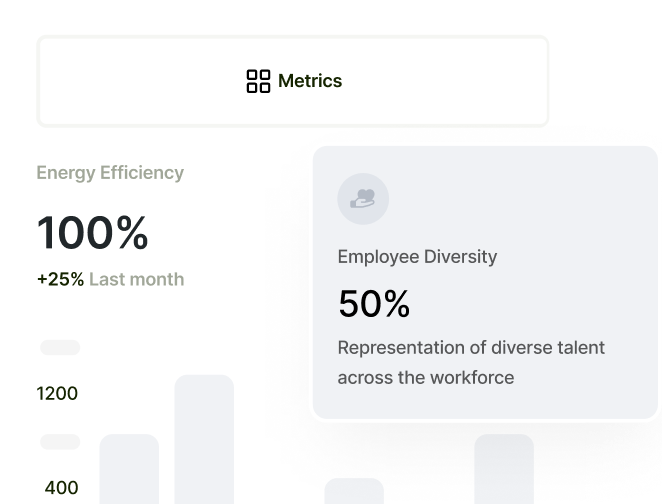
ご連絡の際は右のフォームをご記入いただくか、下記メールアドレスまで直接ご連絡ください。
sales@senecaesg.com7 Straits View, Marina One East Tower, #05-01, Singapore 018936
+(65) 6223 8888
Carrer de la Tapineria, 10
Ciutat Vella, 08002, Barcelona, Spain
+34 612 22 79 06
77 Dunhua South Road, 7F Section 2, Da'an District Taipei City, Taiwan 106414
(+886) 02 2706 2108
Av. Santo Toribio 143,
San Isidro, Lima, Peru, 15073
(+51) 951 722 377